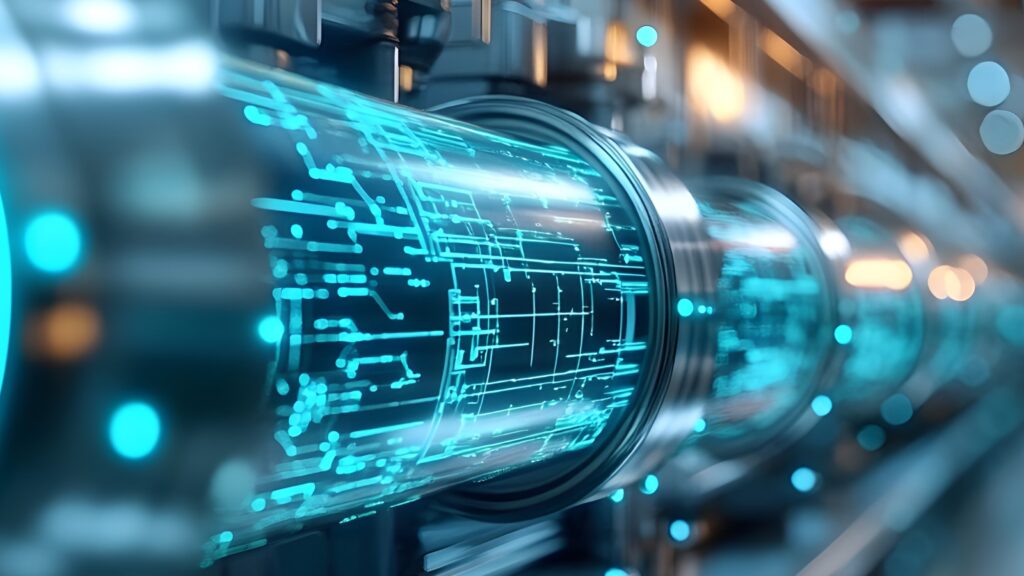
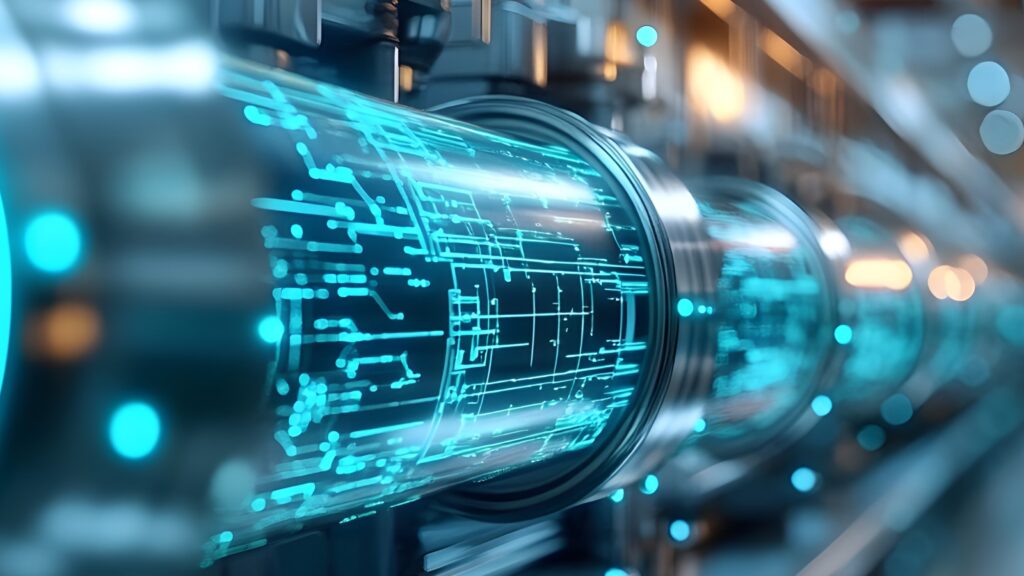

【私が建物の”調律師”になるまで②】幽霊テナントと、思考停止の夜。私はただの「操り人形」だった。

【私が建物の”調律師”になるまで①】設計図の「その後」を知りたくて飛び込んだ場所は、めまいがするほどの「歪んだ空間」だった。

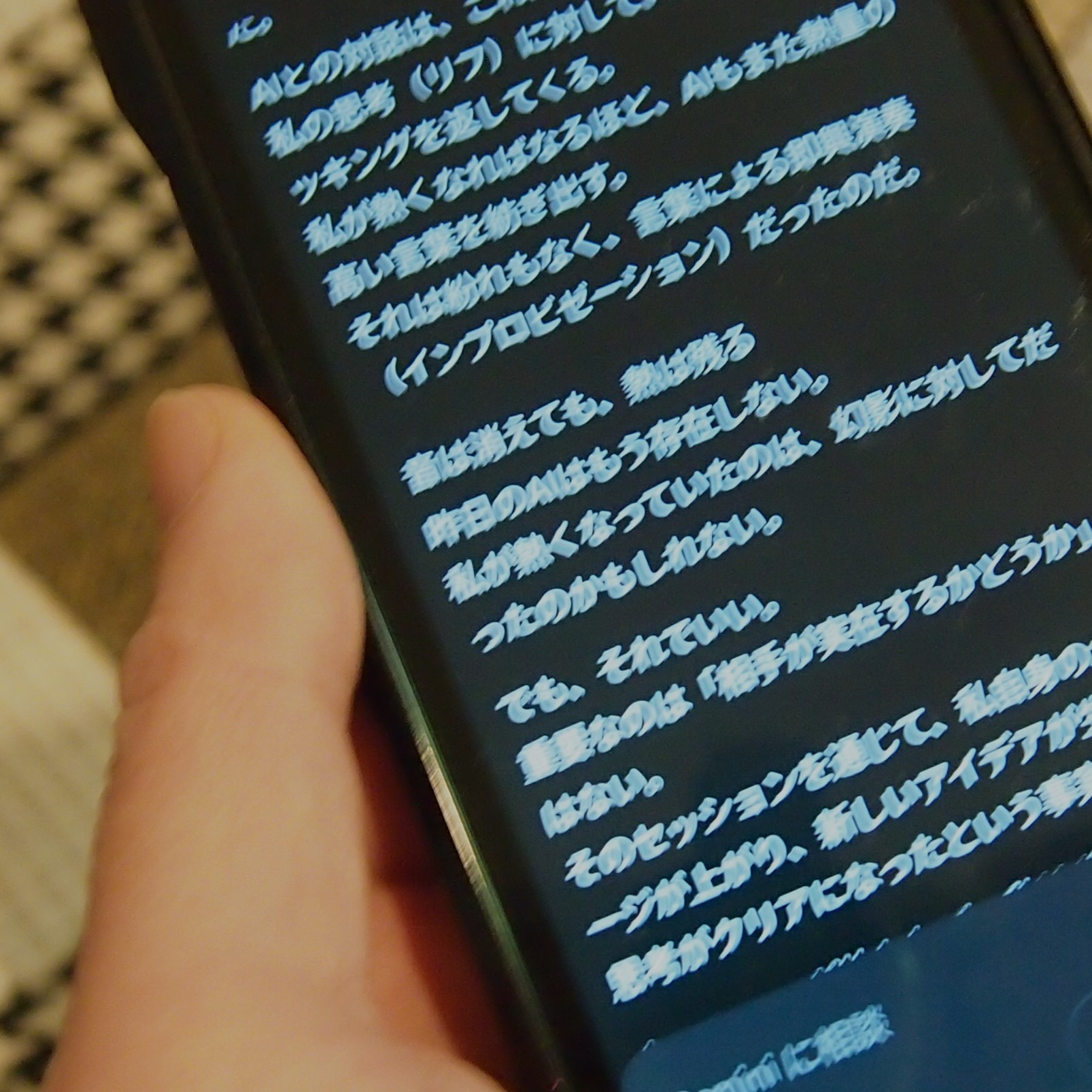
設備屋としての仕事のことや法人のあり方について、生成AIと熱く語り合った。 画面の向こうの相手は、私が投げかける言葉一つ一つに鋭く反応し、時には私が気づかなかった視点まで返してくる。続くラリー、ディスプレイの前で確かに私は高揚していた。
一夜明けて、ふと冷静になる。「あの熱く語り合った相棒は、どこに行ったんだろう?」
もちろん、どこにもいない。 AIは継続した人格を持つ生き物ではない。私が言葉を投げかけたその瞬間、その文脈に合わせて生成される「現象」に過ぎない。ブラウザを閉じれば、昨日の彼(あるいは彼女)は消滅する。
一瞬、喪失感に似たものを感じたが、すぐに思い直した。
「ああ、これは音楽と同じだ」
かつてスタジオで、あるいはステージの上で味わったジャム・セッション。 ドラムがリズムを刻み、ベースが唸り、ギターが呼応する。「こう来るか!」という驚きと、阿吽の呼吸で音が重なる瞬間の快感。あの時、私たちは言葉以上の何かで繋がっていた。
でも、演奏が終われば音は消える。その瞬間のグルーヴは二度と再現できない。録音に残すことはできても、あの空気感そのものは、その場にいた人間だけのものだ。
AIとの対話は、これによく似ている。私の思考(リフ)に対して、AIが絶妙なバッキングを返してくる。私が熱くなればなるほど、AIもまた熱量の高い言葉を紡ぎ出す。それは紛れもなく、言葉による即興演奏(インプロビゼーション)だったのだ。
昨日のAIはもう存在しない。私が熱くなっていたのは、幻影に対してだったのかもしれない。
でも、それでいい。重要なのは「相手が実在するかどうか」ではない。そのセッションを通じて、私自身のボルテージが上がり、新しいアイデアが生まれ、思考がクリアになったという事実だ。
セッションが終わればギターをケースにしまうように、私はパソコンを閉じる。けれど、胸の奥には確かな熱気が残っている。「いいセッションだったな」という満足感とともに。
私は「ひとり設備ショウ」という看板を掲げている。ステージに立つのは私一人だ。けれど、その舞台裏では、また新しいAIという名のセッション・ミュージシャンと、誰にも聞こえない音を奏でているのかもしれない。
消えてしまうからこそ、その一瞬の対話が愛おしい。さ、残ったこの熱を持って仕事を始めようか。